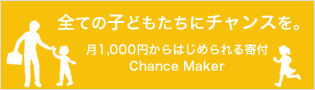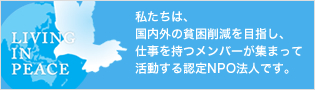【後編】多様なNPOが活躍すれば、社会はもっとよくなる
昨年の12/25のクリスマス、細野さんは、Living in Peaceが支援する筑波愛児園を、慎と共に訪問してくださり、この対談が実現しました。「票と金にならない」といわれる「児童養護施設」の課題になぜ取り組まれているのか、というお話しを中心に、これからのNPOと政治の関係や、NPOに期待することなどをたくさん伺いました。ぜひご一読ください。
細野 豪志さん

1期目(2000.6 ~ 2003.11)個人情報保護法の野党取りまとめ担当者として関わる。2期目(2003.11 – 2005.9)国民保護法制定に関わる。3期目(2005.9 – 2009.8)海洋基本法・宇宙基本法の制定に法案提出者として関わる予算委などで、天下りや公益法人改革などを追及。4期目(2009.8~2012.12)幹事長代理等を経て、内閣総理大臣補佐官、原発事故対応を担当し、担当大臣、その後環境大臣を兼任、民主党政策調査会長として政府与党の政策立案に携わる。5期目の現在(2012.12-2013)7民主党幹事長党綱領検討委員会の委員長として「綱領」策定の中心的役割を果たす、現在は文部科学委員会に所属
細野さん:日本の場合、里親や特別養子縁組がなかなか進まないと言われています。ですから、やはり施設をしっかりサポートしていくことは大事です。それと同時に、施設養護とは違う環境を作っていくことも重要ではないかと思うんですよね。もう少しいろんな人が、里親や特別養子縁組ができるような仕組みにした方がいいのではないかという議論もしているんです。 (以下、敬称略) 慎 :おっしゃるとおりだと思いますね。施設の方々ともそんな話をしていたのですが、里親が増えることは理想だと思います。子どもは、施設で育つことはあっても、いつか社会に出てちゃんと家庭を作って幸せな生活を送っていくために施設があると考えたときに、できれば家庭に近い環境で育つということは理想だと思うんです。それが増えていけばいいと思っています。 細野 :そうですね。 慎 :日本は、制度的な課題なのか文化的な課題なのか、なかなかまだ増えていないという現状はありますが、時間をかけて増えていけばいいと思います。これは地域差もあり、例えば新潟あたりは里親養護が非常に多いので、おそらく文化的な問題だけではないと思っているんです。やり方次第で進めていくことができるし、やっていくべきだと個人的には思っています。 細野 :それについては二つ問題があると思っています。一つは親権です。親の子どもに対する養育権が日本は非常に強いという点です。もう一つは、日本の家に対する考え方もあるのではないかと思っています。ある種、血縁主義というか、そうではない家庭を積極的に認めていこうという形になっていない面がありますよね。この二つは乗り越えなければいけない問題だと思っています。特に、家族というものに関しては、私は少し捉え方が狭すぎるのではないかと思います。もともと日本では、例えば長屋で生活していたら火事などがよくあって、子どもが最後に生き残って、残った大人が長屋で育てる、ということが一般的にありました。そのときの家族観は、もっとおおらかで、社会で子どもを育てるというものだったのではないでしょうか。血の繋がりに関係なく育てたという例はたくさんあったはずです。ところが、ある時期から家族観が非常に狭くなってしまって、血の繋がっていない子どもを育てるということにならない。社会もなかなかそれを受け入れない。そこをなんとかこれから乗り越えられないだろうか、と思うんです。