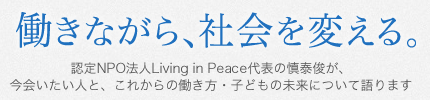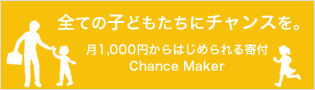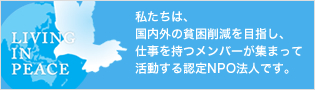第4回
2014年2月25日(火)
衆議院議員 細野 豪志さん × Living in Peace 代表 慎泰俊
【後編】多様なNPOが活躍すれば、社会はもっとよくなる
【後編】多様なNPOが活躍すれば、社会はもっとよくなる
知らない問題を、人は解決しようとしない
慎 :そうですね。根本的な問題を三つとすると、一つ目はやはり今おっしゃった、「人手不足」ですね。ケア職員は単に子どもの世話をする人ではないんです。子どもが生きていくために一番重要なものは、「自分を肯定して努力する能力」「なんとかやっていく力」だと思うんです。それは、基本的には、自分以外の人からの愛情によって育まれるものだと思うのです。

対談中の慎泰俊と細野さん
細野 :そうですね。
慎 :それが今は圧倒的に足りていません。この「人手不足」は一番根本的な課題だと思ってはいるのですが、一方で、施設養護という形態でこれを解決するのはとてもお金かかるんです。
細野 :なるほど。
慎 :例えば、今の職員さんの数を倍にすると、数百億円規模で毎年出ていくお金が変わってきます。そう簡単にできる問題でないということは理解しています。だからこそ里親を増やすなどの代替案が必要だとも思います。しかし、残り十年くらいは、日本では施設養護が常に主流であり続けると思いますので、これは本当にお金を使った方がいいと思っています。ここで子どもが自分の人生を自分でしっかり生きていこうという力がついていくことは大きいです。例えば、今問題になっている生活保護の受給者に施設出身の子どもたちがなることも多いので、それも改善するんですね。
細野 :そうですね、それは大きいですね。
慎 :課題の二つ目は、「家庭的な環境が少ないこと」です。里親養護は社会的養護のまだ一割強にしかなっていませんし、施設も合宿所みたいな施設が多い。これは、子どもが将来家庭をつくるときにすごく困るんですよね。家庭で食卓を囲むことがどういうことなのか、それがいまいち分からないような状態のまま家庭をつくると、いろんなところでつまづきそうになると思うんです。
細野 :なるほど。
慎 :そして三つ目は、違った側面からですが、「社会の認知がほとんどない」ということですね。「児童養護施設」と聞いて、その言葉を理解する人はたぶん10人に1人もいないと思うんです。昔の養護学校を思い浮かべる人が多く、言葉そのものを初めて聞いたという方もいます。孤児院という言葉は知っている方が多いのですが。
細野 :それは、今は使わないですからね。
慎 :はい。認知が圧倒的に足りていないということ、これが先ほどの票にならないという話にも繋がっている気がするのですが、知られていない問題はやはり社会は解決しようとしないので。その三つが、私たちは今なんとかしなければいけないな、と思っている課題です。